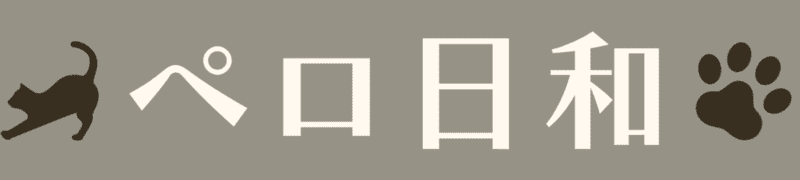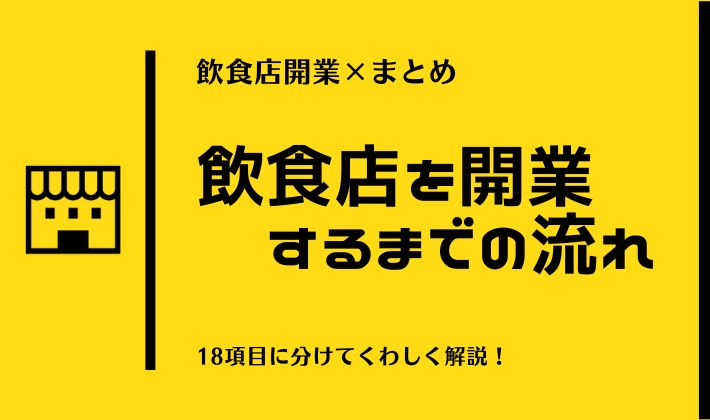飲食店を開業するには、やらなければならない事がいっぱいあってたいへんですよね。
私は今までカフェレストランや居酒屋など、5店舗の飲食店開業にたずさわりましたが、どの店も開業は大変でした。
飲食店の開業に共通する必要なことは、大きく分けるとだいたい次の18項目になります。
- 店のコンセプト設計
- 収支計画書の作成
- 店舗用物件探し
- 店舗名の決定
- 資金調達(創業計画書)
- 保健所への事前相談
- メニュー開発
- 店舗内装設計
- 厨房機器・厨房器具の決定
- 電気・ガス・水道契約、電話番号取得・ネット回線
- 営業許可申請許可(保健所・消防署)
- 人材募集確保
- 販促方法の決定・宣伝ツールの作成
- レジ決済方法の決定
- メニュー表作成
- 営業用口座の作成
- 消耗品の購入
- プレオープン
こうやって見るとたくさんありますが、どれも避けては通れない道ですので1個1個つぶしていかなければなりません。
これら18項目について内容や注意点をまとめましたので開業の参考にしてください。
飲食店開業の流れ1:店のコンセプト設計
飲食店の開業で一番最初にしなければいけないことがコンセプト設計です。
これからどんな新しいお店を作っていくのか、基本的な軸を最初につくる必要があります。
なんとなく儲かりそうなどとふわふわした想いだけで生き残れるほど飲食の世界は甘くないです。
あなたのお店はコンセプトがちゃんと言語化できているでしょうか?
コンセプトのつくり方についてはこちらの記事で紹介しています。
飲食店開業の流れ2:収支計画書の作成
店のコンセプトが決まったら収支を予測してみましょう。
どんな事業でも利益を出し続けていかないとお店はいつかつぶれます。
あなたのお店のコンセプトで、ほんとうに黒字になるのか事前にシュミレーションしておきましょう。
いきあたりばったりの経営では銀行もお金を貸してくれません。
収支計画書をつくる上で考えないといけないのは次の3つです。
- 売上を予測する
- 経費を予測する
- 手元に残るお金を予測する
これらを徹底的にシュミレーションして、不測の事態にも対応できるよう備えておきましょう。
飲食店開業の流れ3:店舗物件探し
飲食店の開業では「立地7割」という有名な言葉があります。
お店が成功するかしないかは立地で7割がすでに決まってるという意味です。
それだけ店舗の物件探しというのは重要です。
あのサイゼリアは、「店長には売上目標を課さない」というのをご存知でしょうか?
お店の売上は「商品」・「立地」・「店舗面積」で決まるため、店長の努力が及ぶところではないからだそうです。
つまり、売上が悪かったらそれは店長のせいではなく、事前のマーケティング不足ということです。
100%のお店に出会えるというのもなかなか難しいですが、なるべくお店のコンセプトに合った店舗に出会うために労力を惜しまず探しましょう。
飲食店開業の流れ4:店舗名の決定
いよいよお店の名前の決定です。
お店の名前をつける時の注意点をまとめました。
- 誰もが読める名前になってるか?
- 商標登録は問題ないか?
- 他店で似たような名前の店がないか?
- ちゃんとググって検索しておきましょう
- パソコンで検索したときにできれば上位にでてきやすい名前が望ましい
- ショルダーネームはつけた方がいいです
ショルダーネームというは、店名の前につける肩書のようなものです。
- 牛一頭飼いの店 焼肉〇〇
- 海と山の幸 居酒屋〇〇
- 地元農家の美味しい野菜料理 〇〇カフェ
店舗名は途中で変更すると、看板やパンフレットなど余計な変更コストがかかるため、最初にしっかりと決めておきましょう。
飲食店開業の流れ5:資金調達(創業計画書)
飲食業の開業には平均で1,000万円ほどかかるといわれてます。
もちろんこれはやろうとしている業種や、店舗が居抜きかどうかによっても大きく変わってきます。
開業資金のすべてを自己資金でまかなえる人は少ないんじゃないでしょうか?
もし開業資金を借りるあてがないのであれば、国金が一番借りやすいのかなと個人的には思います。
国金とは日本政策金融公庫(略称:「日本公庫」)のことで、政府系の金融機関です。
国金でお金を借りるには、まず定型の「創業計画書」を作成する必要があります。
飲食店開業の流れ6:保健所への事前相談
飲食店を営業するためには保健所の営業許可が必要です。
許可をもらうために必要な設備や条件がありますので、店舗の内装設計の前に保健所に一度、相談にいくことをおすすめします。
許可自体は決められたことを守り、保健所に相談しながら進めればそんなに難しい作業ではありません。
飲食店開業の流れ7:メニュー開発
最初に決めたコンセプトを、実際にメニューに落とし込んで提供価格を決定していきます。
メニュー価格を決めるときに気をつけないといけないのが、決して「どんぶり勘定」で決めないことです。
提供する商品の利益を把握してますか?
私は10年間、会計事務所で勤務し色々な会社をみてきましたが、倒産する会社に共通するのが原価管理の甘さでした。
利益が10円の商品を100個売ったところで利益は1,000円です。
利益が200円の商品を5個売った方が早くて楽なのに、原価管理ができてない会社は商品1個の利益すら把握できてません。
原価コストをしっかりと計算して、利益がでるようにメニュー価格を決めましょう。
飲食店開業の流れ8:店舗内装設計から工事
店舗の内装工事については、先程もいいましたが保健所と連絡を取り合いながら進めたほうがいいです。
内装が終わった後に、保健所の許可がおりませんでしたでは、また内装の変更でいらない費用がかかります。
工事前に図面を保健所に見せて、先に同意をもらっておくのが一番です。
あと、ここでもう一度、先に作った収支計画書の総客席数と差異がないかを確認しましょう。
差異があれば数字を変えて、ちゃんと黒字になるか予測をしなおす必要があります。
収支計画書は開業準備のアクションを起こすたびに振り返って数字を確認するようにしましょう。
店舗の内装工事って、当初決めていた金額より膨らんでいくことの方が多いです。
飲食店開業の流れ9:厨房機器・厨房器具の決定
内装設計工事と同時で行うのが厨房機器・厨房器具の選定です。
どこに何を置くかで、今後、営業していくときの作業効率や導線効率に大きく影響してきます。
厨房機器の販売担当者と内装設計者と一緒に細かく打ち合わせをしていきましょう。
今後の業務効率に大きく関わってくるところなので、厨房機器の販売担当者と内装設計者と一緒に、綿密な打ち合わせをしていきましょう。
また、居抜きの場合は、既存の設備が使えるか?壊れそうにないか?などもしっかりと確認しておきましょう。
オープン初日の故障などは目も当てられません。
飲食店開業の流れ10:インフラ会社の決定と契約
下記のインフラは必要ですので会社を選んで契約しましょう。
電気・水道については内装工事の段階で必要になります。
- 電気
- ガス
- 水道
- 電話番号取得
- ネット回線
電話番号については、希望を言えばいくつか候補を教えてもらうことができます。
焼肉店だから「29」が入るとか、0148(美味しい野菜)など、なるべく覚えやすくコンセプトに合った希望番号をもらえるように進めましょう。
飲食店開業の流れ11:営業許可申請許可(保健所・消防署)
内装工事が終わる前に、保健所に営業許可申請を出しましょう。
許可申請を出したあとは、後日、実際に保健所職員により現場で検査が行われます。
開業に必要な資格についてこちらで解説しています。
飲食店開業の流れ12:人材募集
近年、飲食業界は深刻な人手不足となっています。
自分一人でお店を営業するならともかく、従業員がいないと回せないような店舗では、人手不足だと本来のパフォーマンスが出せず売上をあげられません。
私の働いている会社(飲食店)でも、経営の半分ぐらいは人材の悩みで占めています。
今までは単純に時給を上げれば応募も増えましたが、近年では時給を上げても人材の確保が難しくなってきています。
開業直前にあわてないためにも、求人については早めに手を打っておくことをおすすめします。
飲食店開業の流れ13:販促方法の決定・宣伝ツールの作成
お店を開業しただけではお客様はやってきません。
コンセプトに合った、お店の宣伝というのはどうしても必要になります。
幸い、今はSNSという無料で始められる宣伝ツールがあります。
こまめな更新が必要ですが、やらない手はないので、どの媒体を使って宣伝していくか決めてアカウントを作っておきましょう。
時間がかかるものはさっさと外注するようにしましょう。もちは餅屋です。
紙ベースの宣伝媒体(名刺、ショップカード、パンフレットなど)は、ココナラというサービスを使うと安価に依頼することができます。
完全外注すればかなりの時間が節約できると思います。
飲食店開業の流れ14:レジや決済方法の決定
飲食店は現金商売ですのでレジの導入はかかせません。
レジに求める機能は店舗の業態や大きさで変わりますが、小さい飲食店のレジであればつぎの4つの機能があれば十分だと思います。
- 現金決済ができる(普通のレジ機能)
- キャッシュレス決済ができる
- 会計決済のレシートが印刷できる
- 現金を保管できる装置
実際に私の勤める飲食店でもレジを導入してますが、使ってる機能といえば上の4つぐらいです。
また、今はキャッシュレス決済も対応できてないと、お客様が店舗を利用してくれない時代にもなってます。
最近では電子マネーやクレジットカードが使えないお店はほとんどみかけなくなりました。
はじめてのレジなら0円から導入できる、圧倒的高機能なクラウドPOSレジ【スマレジ】がおすすめです。
飲食店開業の流れ15:メニューブックの作成
お客様に見てもらうメニューブックを作成しましょう。
このころには、ほかの準備もあったりして一人では手が回らなくなってると思います。
なので、メニューブックの作成も時間がかかりそうなら、こちらもココナラへ外注した方が早いです。
ココナラのホームページの検索窓でメニューブックで検索するとたくさんの事例がでてきます。
数千円から依頼できますので、思い切って頼んでみた方が断然早いです。
飲食店開業の流れ16:営業用口座の作成
銀行で営業専用の通帳を作りましょう。
会計事務所に勤務していた時、個人口座と事業口座とをまとめて一つにしてた事業主がけっこういましたが、それはやらない方がいいです。
そういう事業主は私生活も事業もごっちゃになっていて、結局、事業も適当で続きませんでした。
事業収益がわかりづらくなって、黒字なのか赤字なのか感覚がマヒしてくるので口座は分けて管理しましょう。
飲食店開業の流れ17:消耗品の購入
制服、レジまわりの備品、洗い場、食器……
飲食店の開業には本当にたくさんの消耗品が必要です。
いるものをちゃんとリストにして買い物に行かないと、買い忘れで何度も何度も買いにいかなくてはなりません。
多分これらの買い物を一発で終わらせられる人いないと思います。
とにかく考えられる限りの物をリストアップしましょう。
飲食店開業の流れ18:プレオープン
オープン前には関係者だけを呼んで、最低1日はプレオープンを行いましょう。
プレオープンは本番前の練習営業です。
いざプレオープンをしてみると、全く想定していなかった問題が次々と出てきます。
まさにそれがプレオープンの狙いなのですが、本オープンで慌てないためにもプレオープンは絶対にやっておいた方がいいです。
関係者や知り合いであれば、多少の失礼があっても許してくれますし、気づいたこともどんどん言ってくれます。
むしろたくさん指摘してもらって少しでもお店を良くしていきましょう。
プレオープンが終わればいよいよ開業オープンとなります!
飲食店の開業後にやること

お店を開業したらまずやらないといけないことが2つあります
それが
- 開業届の提出
- 会計ソフトや税理士の選定
です
開業届の提出
個人が事業を始めたら税務署に出さないといけない書類が「開業届」です。
開業後1ヶ月以内が提出期限ですので速やかに提出しましょう。
会計ソフトや税理士の選定
一人で確定申告まで考えてる人は、会計ソフト使うと簡単便利に申告できます。
実際に私も使ってる会計ソフトをこちらの記事でしょうかしていますので参考にしてください。
会計のことがまったくわからない、そんな暇があれば事業に専念したい。
そんな方は税理士に丸投げするのが一番手っ取り早いです。
最初の内は、わからないことも相談できる税理士に頼むのもいいと思います。
飲食店開業の流れまとめ
以上、飲食店を開業するためのステップを紹介してきました。
飲食店は開業がゴールではなく、むしろここからが本番です。
私は、10年以上会計事務所で働いた経験があり、さまざまな会社が事業を失敗するところをみてきました。
その中には飲食業もいくつかありました。
そして私はいま、法人(飲食業)の総務会計という立場で、10年間、飲食業の世界を中からずっと見続けてきました。
そのうえで断言します!
「飲食の世界は決して甘いものではありません!」
飲食店の生存率は
1年で30%が閉店
2年で50%が閉店
10年で残るのは5%ほど
といわれています。
それでもなお、これから飲食の世界に足を踏み入れて、この厳しい業界で勝ち残っていこうとするのであれば、最後にこの記事を読んで開業の参考にしてもらえればと思います。
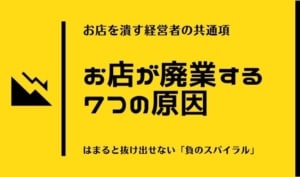
-
飲食店のコンセプトは面白いだけでいい?作り方は5W2Hで
-
創業計画書の記入例(飲食店の場合)日本政策金融公庫からの借入方法
-
飲食店の収支計画書(開業前に収支を予測してみよう)
-
飲食店が売上アップさせるために考えるべき16のこと
-
飲食店物件の探し方(情報収集のコツや確認すべき10項目)
-
飲食店の営業許可の条件は?(ポイントは営業設備の事前相談)
-
飲食店開業に必要な届出(個人事業開業届・青色申告)の書き方
-
開業後の会計ソフトに1年間無料の弥生会計をおすすめする理由
-
飲食店の損益分岐点はいくら?(一日に必要な売上の出し方)
-
アルバイトが扶養を外れる給料の上限はいくらまで?(所得税・社会保険)
-
飲食店の開業に必要な「2つの資格」|経営に有利な資格一覧
-
飲食店の原価率と計算式の基礎!原価を下げる方法は?
-
飲食店が人手不足で回らない!クレームになる前に求人対策!
-
飲食店の開業を失敗する理由【負のスパイラルと7つの原因】
-
飲食店を開業するまでの流れを解説【準備すべき18項目】
-
abc分析のやり方をわかりやすく解説(飲食店の場合)
-
飲食店の消費税の計算方法をわかりやすく解説
-
飲食店にかかる経費一覧【削減ポイントを中の人が解説】
-
飲食店の税理士費用はいくら?相場を元会計職員が教えます!